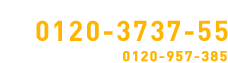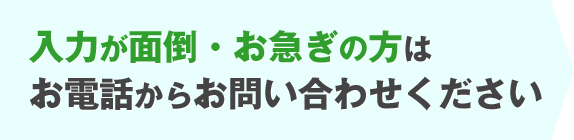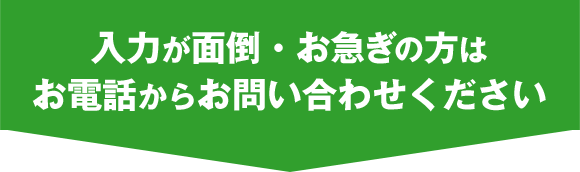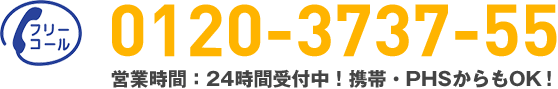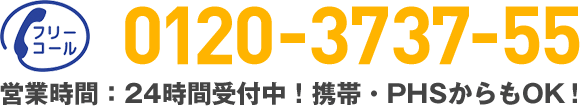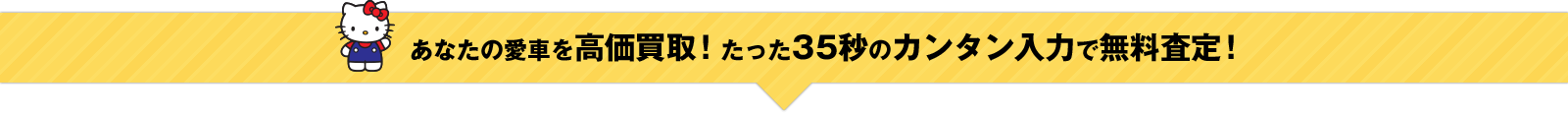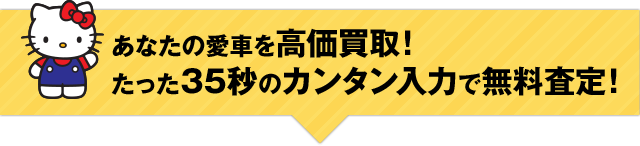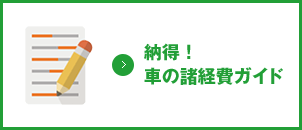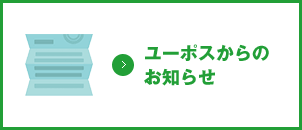廃車ってどうやって行うの?廃車手続きについて紹介します。
車が不要になったときには売却のほかに廃車という方法があり、使わない車を廃棄したりする際の手続きです。
廃車には永久抹消登録と一時抹消登録の2種類があり、また普通車と軽自動車でも差があります。
この記事では廃車についての手続きや細かい違いについてご紹介します。
このページの目次
廃車ってどういう状態?
廃車とは車の「車籍」を抹消する手続きを指しており、主に不要な車の処分方法になります。
廃車は不要な車の処分方法
車の車籍とは、一台一台の車に割り当てられた戸籍のようなものであり、車籍が残っている限り、車の所有者には自動車税の納税義務が発生します。
そのため、もし車が不要になった場合には、廃車手続きを行うことで正式に手放すことができます。
車が不要になるシチュエーションにはいくつかありますが、ライフスタイルの変化によってそれまでの車に乗らなくなったり、事故や故障で車が動かなくなったりした場合が考えられるでしょう。
廃車手続きを行った車は登録が抹消されますので、公道走行はできなくなります。
廃車には永久的な廃車の手続きと、一時的な廃車手続きの2種類があります。
また普通車と軽自動車では手続きの方法や届出先などが違いますので、それぞれ詳しくご説明します。
▼あわせて読みたい記事▼
廃車にかかる費用ってどのくらい?手続き方法までしっかり解説します
普通車の廃車の種類
普通車は軽自動車を除くすべての乗用車を指しており、普通車の廃車には「永久抹消登録」と「一時抹消登録」の2種類があります。
普通車は登録を陸運局、もしくは陸運支局で行いますので、廃車手続きも陸運局などに届けます。
永久抹消登録とは
永久抹消登録は車の解体を伴った廃車手続きのことで、車を完全に使用停止する場合に行われます。
永久抹消登録は必ず車自体の解体が必要で、解体されていない状態では永久抹消登録はできません。
永久抹消登録はもう二度とその車に乗る必要がない場合や、事故などで修理不能な車を処分する場合に利用します。
永久抹消登録をした車は解体業者や廃品業者などに引き渡されており、そこで部品になったりスクラップとなったりして再利用されます。
一時抹消登録とは
一時抹消登録は車の解体は行わずに廃車を行う手続きで、車自体は残ります。
一時抹消登録を行うのは一時的に車の使用を停止したい場合です。
車を登録したままでは税金の納税義務が発生するため、車は残しながら登録だけを抹消します。
そのため永久抹消登録のように解体も必要なく、書類上の手続きのみで行われます。
一時抹消登録をした車はもう一度登録することも可能で、再度車検を受けて合格することで公道走行可能な状態に戻ります。
この再利用可能な点が永久抹消登録との最大の違いです。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録で車を手元に残した状態で、その後に解体したくなった際には、一時抹消登録後の解体届出を行います。
一時抹消登録後の解体届出を行う場合、永久抹消登録と同じく車の解体が前提となります。
一時抹消登録を行った段階で車は公道走行できなくなりますので、車の移動には陸送などが必要でしょう。
軽自動車の廃車の種類
軽自動車は排気量や車のサイズが決められた日本独自規格の車で、廃車手続きに関して普通車と異なる点があります。
軽自動車の登録は「軽自動車検査協会」で行われており、普通車とは届出先が違います。
そのため廃車手続きも軽自動車検査協会に届け出ることになります。
軽自動車の廃車手続きは「解体返納」と「一時使用中止」があります。
解体返納とは
解体返納は普通車の永久抹消登録同様に、車の解体を伴う廃車手続きです。
軽自動車が不要になって車籍を抹消したい場合や、事故や故障などで軽自動車が使用不能になった場合に行う手続きです。
解体は普通車と同じく解体業者や廃品業者にてスクラップにしますが、その後に届け出するのが軽自動車検査協会になります。
一時使用中止とは
一時使用中止は普通車の一時抹消登録と同様の手続きで、車自体は残しながら登録だけ抹消します。
軽自動車も登録をしたままでは税金の支払いが発生しますので、車を残したまま一時的に登録抹消したいときに一時使用中止手続きを行います。
一時使用中止の届け出も、解体返納と同じく軽自動車検査協会となります。
一時使用中止後の解体届け出
軽自動車でも一時使用中止の後に解体したい場合は、一時使用中止後の解体届け出が行なえます。
輸出抹消について
廃車手続きは普通車の永久抹消登録と一時抹消登録(軽自動車の場合は解体返納と一時使用中止)に大きく別れますが、もう一つ「輸出抹消」という廃車手続きもあります。
輸出抹消手続きは個人ではほとんど関わることのないものですが、車を海外へ輸出する際に登録抹消するための手続きです。
登録済みの車の輸出抹消はもとより、一時抹消登録済みの車も輸出抹消手続きを取ることができます。
普通車は輸出抹消手続きも陸運局、陸運支局で行います。
また軽自動車の場合は同様の手続きとして「輸出予定届出」という手続きがあり、軽自動車検査協会にて手続きを行います。
普通車の永久抹消登録の流れ

ここからはそれぞれの廃車手続きの流れをご紹介します。
永久抹消登録には以下の書類が必要となります。
|
永久抹消登録必要書類 |
概要 |
|
自動車検査証(車検証) |
・車検証原本(ダッシュボード内に収納) |
|
実印・印鑑登録証明書 |
・車の所有者の印鑑証明(発行から3カ月以内) ・実印 |
|
ナンバープレート |
・前後2枚を用意 |
|
解体報告記録日・移動報告番号の控え |
・解体業者、リサイクル券などで確認 |
|
永久抹消登録申請書 |
・廃車手続き時に運輸支局で入手 |
|
手数料納付書 |
・廃車手続き時に運輸支局で入手 |
|
自動車重量税還付申請書 |
・自動車重量税の還付を受ける場合に作成 |
|
委任状 |
・所有者以外の人が廃車手続きを行う場合に必要 |
①必要書類の用意
まずは車検証、印鑑登録証明書を用意します。
車検証は車に備え付けてありますので、印鑑登録証明書を市区町村の役場で取得しましょう。
②解体業者の選定
永久抹消登録には手続き前に車を解体することが前提なので、解体業者の選定が必要です。
車の解体は自動車解体業者や廃品回収業者などが行っており、解体の依頼は個人でも可能です。
車の移動を伴いますので、車の保管場所から近い業者を探すとよいでしょう。
③解体業者への車の持ち込み&解体作業実施
解体業者が見つかったら、次は実際に車の解体作業に移ります。
廃車にする車が自走できればそのまま持ち込むことも可能ですが、動かない場合や事故車、故障車の場合は陸送しなければなりません。
解体業者が引き取りも行っている場合が多いため、持ち込み方法は相談しましょう。
車の持ち込み後に解体業者にて解体作業が実施されます。
④解体業者の報告書(解体証明)の取得
車の解体が完了すると、解体業者から証明書が発行されます。
また車についていたナンバープレート前後2枚が取り外されていますので、これも解体業者から受け取りましょう。
証明書は「解体報告記録日・移動報告番号の控え」という形で発行されますので、これが解体完了の証明になります。
⑤陸運局で必要書類記入、書類提出
必要書類をそろえた上で陸運局へ行き、そこで「永久抹消登録申請書」や「手数料納付書」を入手、必要事項を記入して提出します。
また廃車手続きをほかの人や代行業者に依頼する場合は、委任状も用意しましょう。
廃車手続きは基本的に平日しか受け付けていませんので、日中に仕事がある方は代行業者にお願いするほうがスムーズです。
⑥陸運局でナンバープレート返納
書類が受理されたら、次に取り外したナンバープレートを陸運局の窓口で返納します。
ナンバープレートの返納をもって廃車手続きは完了となります。
なお2017年の法改正により、返納するナンバープレートを記念として持ち帰ることができるようになりました。
持ち帰りを希望する場合は、窓口でその旨を伝えて所定の手続きを行いましょう。
⑦陸運局で自動車重量税還付手続き
廃車に伴って自動車重量税の還付を希望する場合は、同日に陸運局で還付手続きも行いましょう。
必要書類の記入時に同時に申請し、振込先の金融機関などを記載します。
普通車の場合は廃車にした場合のみ自動車重量税の一部が還付できるので、ぜひ還付を受けましょう。
還付金は申請からおよそ2カ月後をめどに指定の金融機関に振り込まれます。
普通車の一時抹消登録の流れ
普通車の一時抹消登録に必要な書類は以下となります。
永久抹消登録より必要書類の種類は少なくなっています。
|
一時抹消登録必要書類 |
概要 |
|
自動車検査証(車検証) |
・車検証原本(ダッシュボード内に収納) |
|
実印・印鑑登録証明書 |
・車の所有者の印鑑証明(発行から3カ月以内) ・実印 |
|
ナンバープレート |
・前後2枚を用意 |
|
一時抹消登録申請書 |
・廃車手続き時に運輸支局で入手 |
|
手数料納付書 |
・廃車手続き時に運輸支局で入手 |
|
委任状 |
・所有者以外の人が廃車手続きを行う場合に必要 |
①必要書類の用意
まずは一時抹消登録に必要な書類として、車検証と印鑑登録証明書を用意しましょう。
車検証は車に備え付けてありますので、市区町村の役所で印鑑登録証明書さえ入手すれば書類がそろいます。
②ナンバープレート取り外し
一時抹消登録では車自体は解体しませんので、永久抹消登録のように解体業者とのやりとりはありません。
その代わり車のナンバープレートはユーザー自身で取り外す必要があります。
ナンバープレートは車の前後バンパーやテールゲートにネジで固定されていますが、そのうちの一つは「封印」がついているため注意が必要です。
封印は後側の左側ネジにカバーのようについており、封印を壊さない限りナンバープレートが取れないようになっています。
一度封印を壊すと公道走行は違法となりますので、一時抹消登録をするとき以外は取り外してはいけません。
封印はドライバーなどでこじ開けるだけで壊せますので、その後はプラスドライバーでネジを外してナンバープレートを取り外せます。
その後の一時抹消登録にはナンバープレート2枚のみが必要で、封印やネジなどは不要です。
③陸運局で必要書類記入、書類提出
一時抹消登録の手続きを行うために、車検証、印鑑登録証明書&実印、ナンバープレート前後2枚を持って陸運局(陸運支局)へ行きましょう。
一時抹消登録では車本体を持っていく必要はありませんので、車は自宅などに保管したままです。
陸運局では一時抹消登録申請書と手数料納付書に必要事項を記入し、そのほかの必要書類とともに提出します。
一時抹消登録では手数料が350円必要なので、これは陸運局の窓口で印紙を購入して台紙に貼って支払います。
なお一時抹消登録を代行業者に依頼する場合は、委任状も必要です。
④陸運局でナンバープレート返納
書類が受理されたら、次は持ってきたナンバープレートを返納します。
ナンバープレートを窓口に提出して完了です。
なお一時抹消登録の場合でもナンバープレートの持ち帰りも可能で、永久抹消登録と同じく窓口でその旨を伝えれば手続きができます。
⑤登録識別情報等通知書が交付
一時抹消登録では最後に「登録識別情報等通知書」が交付されるので、忘れずに受け取りましょう。
登録識別情報等通知書は一時抹消登録が完了したことの証明書で、この書類をもって自動車税の支払い義務が停止します。
一時抹消登録した車は後から再登録することで再度公道を走行させることができますが、その際にも登録識別情報等通知書が必要となります。
登録識別情報等通知書は紛失すると再発行が不可能な書類なので大事に保管しなければなりませんが、万が一紛失した場合は別の書類を用意して証明する方法があります。
なお一時抹消登録では永久抹消登録のように自動車重量税の還付は行われません。
軽自動車の解体返納の流れ
軽自動車の解体返納では普通車の場合と一部違う部分があります。
なお解体返納手続きに対する費用は無料ですが、別途車の解体費用が必要です。
まずは解体返納に必要な書類をご紹介します。
|
解体返納必要書類 |
概要 |
|
自動車検査証(車検証) |
・車検証原本(ダッシュボード内に収納) |
|
使用済自動車引取証明書 |
・解体業者から入手、リサイクル券番号の記入が必要 |
|
ナンバープレート |
・前後2枚を用意 |
|
解体届出書 |
・廃車手続き時に軽自動車検査協会で入手 |
|
軽自動車税申告書 |
・地域によって必要な場合あり |
|
申請依頼書(委任状) |
・所有者以外の人が廃車手続きを行う場合に必要 |
①必要書類の用意
軽自動車の解体返納では普通車と違って印鑑登録証明書などは不要なため、事前に用意する書類は車検証のみです。
②解体業者の選定
解体返納手続きにも車の解体が前提になりますので、解体業者の選定が必要です。
解体に関しては普通車、軽自動車問わず解体業者や廃品業者が受け付けていますので、費用や輸送の利便性などを考えて選びましょう。
③解体業者への車の持ち込み&解体作業実施
解体業者が決まったら車を業者へ持ち込み、解体作業が実施されます。
軽自動車の場合も車を業者まで移動させなければなりませんので、自走するか陸送、もしくは解体業者の引取を手配して輸送しましょう。
④解体業者の報告書(使用済自動車引取証明書)の取得
軽自動車の解体が完了したら、その証明書として「使用済自動車引取証明書」が発行されます。
この書類が普通車の永久抹消登録と違う点です。
また併せて取り外したナンバープレート前後2枚も受け取ります。
⑤軽自動車検査協会窓口で必要書類記入、書類提出
解体が完了して解体業者から書類とナンバープレートを受け取ったら、次は必要書類を持って軽自動車検査協会で廃車手続きを行います。
軽自動車検査協会では「解体届出書」に必要事項を記入し、そのほかの必要書類とともに提出します。
また代行業者に手続きを依頼する場合は、「申請依頼書」の記入、提出も必要です。
⑥軽自動車検査協会窓口でナンバープレート返納
提出した解体届出書が受理されたら、次はナンバープレートを軽自動車検査協会の窓口で返納します。
なお軽自動車の場合もナンバープレートの持ち帰りが可能なので、希望する場合は窓口で申請を行いましょう。
⑦軽自動車検査協会にて軽自動車税の支払い停止手続き
軽自動車の解体返納では、軽自動車税の支払い停止手続きが必要な場合があります。
軽自動車税の扱いは市区町村によって違いがありますので、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で確認しましょう。
⑧軽自動車検査協会窓口で自動車重量税還付手続き
軽自動車も解体返納の場合には自動車重量税の還付が可能です。
自動車重量税の還付手続きには振込口座、マイナンバーなどの記載が必要です。
軽自動車の一時使用中止の流れ
軽自動車の一時使用中止の流れを紹介しますが、車の解体を行わないので用意するものは少ないです。
|
解体返納必要書類 |
概要 |
|
自動車検査証(車検証) |
・車検証原本(ダッシュボード内に収納) |
|
ナンバープレート |
・前後2枚を用意 |
|
自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書 |
・廃車手続き時に軽自動車検査協会で入手 |
|
軽自動車税申告書 |
・地域によって必要な場合あり |
|
申請依頼書(委任状) |
・所有者以外の人が廃車手続きを行う場合に必要 |
①必要書類の用意
一時使用中止手続きに必要な書類は車検証のみですので、車から取り出しておきましょう。
②ナンバープレート取り外し
軽自動車もナンバープレートをユーザーが取り外す必要があり、前後2枚のナンバープレートを普通車同様の方法で取り外します。
③軽自動車検査協会窓口で必要書類記入、書類提出
一時使用中止手続きも軽自動車検査協会で行いますので、車検証と取り外したナンバープレートを持って手続きを行います。
一時使用中止の場合には申請書として「自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書」が必要ですので、軽自動車検査協会で入手して必要事項を記入しましょう。
その際手数料として350円が必要となるため、印紙代として支払って台紙に貼りましょう。
また一時使用中止の手続きを代行業者に依頼する場合は、申請依頼書の記入も必要です。
④軽自動車検査協会窓口でナンバープレート返納
一時使用中止の申請書が受理されたら、次は窓口でナンバープレートを返納します。
一時使用中止の場合でもナンバープレートの持ち帰りは可能ですので、希望する場合は申請しましょう。
⑤自動車検査証返納証明書が交付
一時使用中止手続きが完了した際に「自動車検査証返納証明書」が交付されますので、忘れずに受け取りましょう。
自動車検査証返納証明書は軽自動車税の支払い義務停止の証明書であり、また再登録の場合にも必要な書類です。
紛失してしまうと再発行は不可能ですが、その場合いくつかの書類をそろえて申請することで再登録などは可能です。
⑥軽自動車検査協会にて軽自動車税の支払い停止手続き
一時使用中止の場合でも、軽自動車税の支払い停止手続きが必要な場合があります。
こちらも市区町村によって制度が違いますので、軽自動車検査協会に隣接する窓口で確認してください。
廃車にせず買取に出す方法も
普通車や軽自動車はユーザーの事情や事故、故障などで廃車にしなければならないシーンがありますが、その車を買取に出す方法があります。
廃車にする車は不動車や事故で走行不能になった車が多いですが、近年ではそういった車でも買取を行う業者が増えてきています。
一般的な中古車として買い取れない車でも、部品取り用の車や修理ベースとしての需要があり、ある程度の買取金額で引き取る業者もあります。
廃車する際に解体費用などがかかるのであれば、その前に一度査定を受けてみて、買取可能かどうか確認するほうがお得でしょう。
車の買取専門店であるユーポスでは、不動車、事故車の買取、引取を行っています。
もし車の廃車をお考えの際は、その前に一度ユーポスへご相談ください。
まとめ
車が不要になったり事故や故障で使用不能になったりした際には廃車が必要で、状況や車の状態によって完全な廃車か一時的な廃車かを選びます。
普通車、軽自動車によっても手続きが違い、必要書類や届出先が変わりますので、本記事を参考に適切な手続きを行いましょう。
ユーポスでは車買取専門店のメリットを生かした高額買取を実施しており、余計な経費を削減することで買取金額へ反映しています。
不動車や事故車の引取、買取も行っておりますので、ご希望の方はぜひ当社のサイトより無料査定をご利用ください。
▼あわせて読みたい記事▼